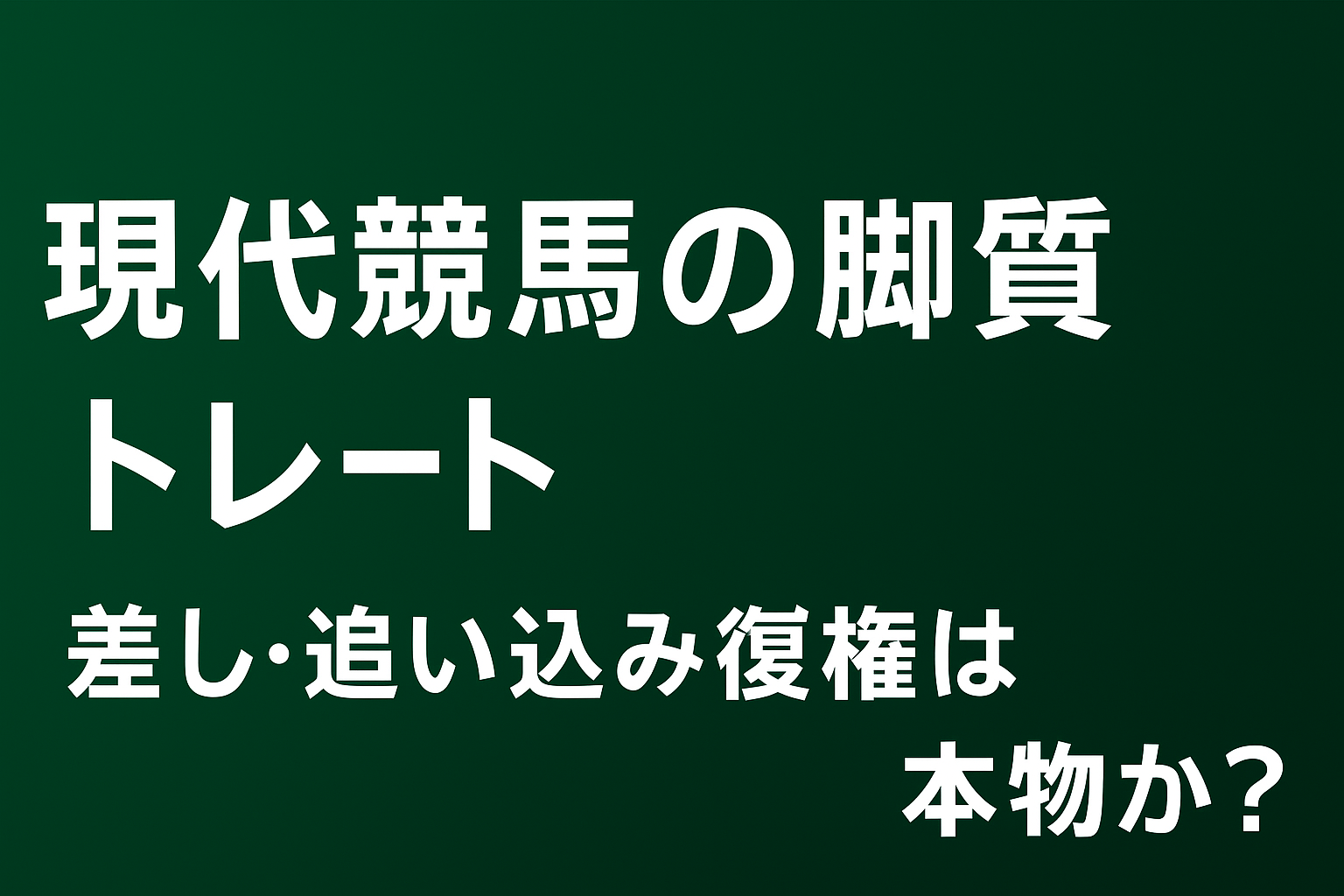馬場傾向、調教の進化、騎手の戦術変化
目次
序章:差し・追い込み勢が再び主役に?
かつて競馬は「逃げ・先行有利」の時代が長く続いた。 特に2010年代前半は、馬場の高速化が進んだことで、ペースが緩みやすい中距離戦を中心に、 前で運んだ馬がそのまま押し切る競馬が主流だった。
しかし2020年代に入ると状況は一変。 イクイノックス、リバティアイランド、ジャスティンパレスなど、 中団~後方から鋭く伸びる馬たちがGⅠの主役となってきた。
では、この「差し・追い込み復権」は一時的な流れなのか、それとも確実なトレンドなのか。 その背景と構造を、ラップ・馬場・騎手技術の観点から深掘りしていく。
なぜ先行優位時代は長く続いたのか
まず、かつて先行有利が定着していた要因を整理したい。
主な理由は次の3つだ。
- ①高速馬場により全体ラップが軽く、前が止まりにくい
- ②上がり勝負になりやすく、後方勢が届く時間が足りない
- ③逃げ・先行勢のレベルが高かった
特に「②後方勢の距離不足」は大きかった。 直線が長い東京ですら、0.5秒前半の緩い中盤を刻まれると差しは届きにくかった。
この「中盤の緩み」は、馬場・騎手心理・調教技術など複合的要因によって生まれ、 10年以上にわたり、先行優位を支えてきたとも言える。
近年のGⅠで顕著な“差し決着”の増加
しかしここ数年、GⅠの決着傾向は明らかに変化した。
天皇賞(秋)イクイノックス ジャパンカップ タイトルホルダー捕える競馬が主流 大阪杯 差し決着多発 桜花賞・オークス 中団~後方馬が台頭 マイルCS・安田記念 差し馬が上位を独占
特に2023~2025年は、直線半ばから一気に伸びてくる馬たちが台頭し、 先行勢が苦戦するパターンが顕著だ。
これは単なる偶然ではなく、構造的な変化が起きていると見るべきだろう。
差しが復権した3つの背景
差しが強くなった背景には、大きく3つの要素がある。
- ①馬場の均質化と“フラット化”
- ②ラップの質が変化し、持続力戦が増加
- ③騎手戦術が進化し、中団~後方の精度が上がった
これらが組み合わさることで、 「差しが届きやすい構造」へと中央競馬そのものが変化してきたのである。
ラップ構造の変化と「中盤緩み」の減少
実は、近年の中央競馬では“中盤が緩まないレース”が増えている。
先行馬同士の牽制が弱まり、 むしろ平均的に流れるパターンが多くなった。
特に中距離GⅠで顕著だが、 「12.0前後のラップを刻み続ける」持続戦が主流となり、 これが後半の切れ味に優れた馬に有利に働いている。
中盤が緩まない → 前が苦しい → 差しが届く
この構図は、京都改修後の2200m・2400m、阪神の内回りでも見られる。 つまり、コースに関係なく“構造的に差し優位なラップ”が増えたのだ。
馬場造園技術の進化と脚質傾向
馬場造園課の技術進化により、 2020年代の芝は「以前ほど前が止まらない高速馬場」ではなく、 むしろ「全体的にフラットで消耗戦になりやすい馬場」へ移行している。
以前は芝の回復スピードが極端に速く、開幕週は完全に前有利。 しかし近年は開催の前後で“差の少ない馬場”を目指す傾向が強い。
これにより、差し・追い込み勢の台頭が増えた形だ。
騎手戦術の変化:トップジョッキーの狙い所
トップ騎手が「無理に前へ行かない」ケースが増えている。
ルメール、川田、横山武、ムルザバエフなどは、 展開を読みつつ中団で脚を溜める意識が強く、 勝負どころで“確実に加速できる位置”を選ぶ傾向にある。
これにより、差し馬の勝率・複勝率は確実に上昇している。
追い込み馬が勝つための“絶対条件”
差し・追い込みが強くなったとはいえ、 後方一辺倒の馬が常に勝てるわけではない。
追い込みが決まる条件は明確だ。
- ①縦長で流れる展開
- ②中盤が緩まない
- ③馬群の外へ進路確保しやすいコース
- ④トップジョッキーの手が回る
特に「中盤が緩まない」ことは絶対条件だ。 これがない限り、追い込みは届かない。
つまり、ただの後方勢ではなく、 “中盤の持続力に優れたタイプ”が現代で強い追い込み馬となる。
差し・追い込み全盛期は今後も続くのか?
結論から言えば、現在の傾向はしばらく続くと考えられる。
理由は3つ。
- 馬場造園の方向性が変わらない
- 平均ペースの持続戦が増え続けている
- トップジョッキーの乗り方が進化し続けている
特に持続力戦の増加は、差し勢にとって追い風だ。 近年のクラシック戦線でも中団からの差しが主流になりつつあるのは、 この流れを象徴している。
結論:脚質トレンドは「均衡時代」に突入へ
2020年代の競馬は、「逃げ・先行」「差し・追い込み」の優劣というより、 レースごとに“脚質傾向が変動する均衡状態”にあると言える。
ペース次第では前が残り、 馬場や展開ひとつで差しが一気に台頭する。
つまり、現代競馬の本質は――
「脚質の固定観念に縛られず、レース構造を読むこと」
調教進化、馬場技術の発展、騎手の戦術理解の向上。 これらが相まって、脚質トレンドはより複雑化している。
そして、その“複雑さの中にこそ”予想の妙味は潜んでいる。